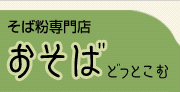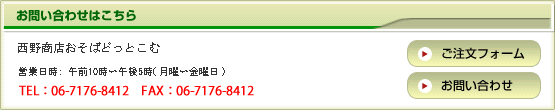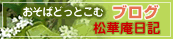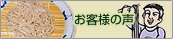そば粉辞典3.そば粉レシピ
日本にそば切りが定着したのは、つなぎ粉を使うようになった江戸時代ごろとか。
それ以前は、「そば団子」「すいとん」「お焼き」のような形で食べられていました。
世界各地で栽培されているそば。こちらでは、そば粉のおいしい食べ方をお教えします。
|そばがき|そば茶入り そば粥|ガレットとそば粉のクレープ|そば粉を使ったあべかわ|そばぜんざい|
-
二八そばの打ち方はこちらです。
ガレットを作りたいとのご希望で そば粉をお買い求め頂いたお客様から、うれしいメールを頂きました。
「そば粉とお水とお塩をこね合わせて、お湯で茹でて きな粉をつけて 試食してみました(^○^)
50グラムのそば粉はあっという間に、私のおなかの中へ吸い込まれていきました。
これだったら、きな粉だけでなく あんこをのせても手軽なおやつが いつでも簡単に食べれそうです。
先ほど 朝食と昼食かねて 作ってみました。
「肉じゃがでも大丈夫」と教えて下さった事を思いだして、残り物のキンピラだとか、千切り大根煮物を
具材にしてみました。
う〜〜っ、とってもおいしくおなかの中へ…(^o^)
これから和の食材にて 飽きないで色々工夫して 楽しめそうです。この小さな幸せにワクワク…」
そば粉を 日常の食生活の仲間になさってみては 如何でしょうか?
そばがき
- 「椀がき」と「鍋がき」
- そば粉の栄養を余すことなく摂取できる食べ方は、なんといっても「そばがき」。単純な料理法ながらも、非常に奥の深い一品です。ちなみにそばがきには、「椀がき」と「鍋がき」の2種類があります。
単純な作り方のようで、奥が深いそばがき。硬すぎても、柔らかすぎてもおいしくないため、絶妙な硬さが求められます。ただし、うまく出来上がったそばがきは絶品! まだ召し上がったことがないという方は、ぜひチャレンジしてみてください。
────────────────────────────────────────────
【椀がき】
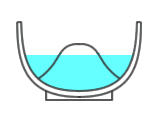

当社2代目社長は、お客様にそばがきの作り方を問われると、いつもこのような図を描いて説明していました。
山型にそば粉を入れて、熱湯を入れ、一気にかき混ぜる。
当店ではいつも、こうして作っています。
(食後の片付けが楽です)
■お湯の量はそば粉の種類により異なります。
三番粉(田舎そば)は、そばの山の7〜7,5合目
二番粉(ちゅうそう粉)は、そばの山の8〜8.5合目
一番粉(更科粉)は、そばの山の9〜9,5合目・・・が目安になります。
〔例えば一番粉としてお買い求められた場合でも、各店のそば粉により、お湯の量が異なることが
ございます〕
おいしく作るには、お湯の量を過不足なくすることです。
器はそば粉に対して大きめの方が良いと思います。 お湯を入れると量が増え、混ぜ辛くなります。
材料
- そば粉 100g
そば粉の種類は問いませんが、種類によって食感はかなり違ってきます。
初めて召し上がる方は、ざらつき感が少なく、のど越しが良い更科粉(一番粉)・ちゅうそう粉を
お奨め致します。
食べ慣れた方は、田舎そば用のそば粉もお楽しみください。
そば粉はふるいにかけた方がなめらかな食感になります。(鍋がきも同様です)- 熱湯
そば粉の1.2〜2倍ぐらいを用意します。 硬さ・柔らかさはお好みで調整してください。
椀がき 調理方法
 少し大きめの深い器を用意して、温めておいてください。
少し大きめの深い器を用意して、温めておいてください。
器の中にそば粉を山型に入れます。
その際、量はやや控えめに。熱湯を注ぐことで、想像以上に分量が増えるため気を付けてください。
 山型を崩さないように、そば粉の周りに熱湯を注ぎます。
山型を崩さないように、そば粉の周りに熱湯を注ぎます。
更科粉は山の9合目ぐらいまで、田舎そばのそば粉は7合目ぐらいを目安にしてください。
 練りかけた状態です。
練りかけた状態です。

![]()
練り始めはまとまりにくいと思いますが、あきらめずに頑張ってください。
後はひたすら、大きく円を描くように練り続けます。
熱湯を注ぎ足すのは厳禁! うまく混ざらないことがあります。
どうしてもと言う場合は、出来るだけ早い段階で足してください。
 ほぼ完成しました。
ほぼ完成しました。
きめが細かく、しっとりとした感じに仕上がれば成功です。
 器のままでも良し お皿などに移し変えても良し。
器のままでも良し お皿などに移し変えても良し。
写真は生じょうゆにつけて食べていますが、麺つゆなどでもおいしくいただけます。
薬味として、ねぎ、おろし大根、わさびなどを添えてください。
【鍋がき】
【鍋がき】 調理方法
鍋を使います。
材料は椀がき同様、そば粉と水。 ただし、水の量はそば粉の約2倍ほど用意してください。
椀がきに比べて手間がかかる分、仕上がりのきめは細かく、食感はなめらかです。
 椀がきと同S様、鍋にそば粉を山型に入れます。
椀がきと同S様、鍋にそば粉を山型に入れます。
 水を加えます。
水を加えます。
 だまにならないように混ぜ合わせます。
だまにならないように混ぜ合わせます。

![]()
糸がひくくらいに、しっかりと混ぜ合わせます。
 火加減に注意しながら焦げつかないようにかき混ぜます。
火加減に注意しながら焦げつかないようにかき混ぜます。
水分が蒸発して、そば粉が硬くなりすぎないように!
ねばりけが出てくると、固まる速度が速まるので、手早く練ってください。
 焦げつきに注意!
焦げつきに注意!
頃合いを見て、火から下ろし、さらになめらかになるように練り合わせます。
 形を作るときに、やけどをしないように気を付けてください。
形を作るときに、やけどをしないように気を付けてください。
そば屋さんではよく木の葉型にしていますが、ご自宅ではお好きな形にして、お湯に浮かせれば出来上がりです。
 いただきます! 薬味などは椀がきと同じ。
いただきます! 薬味などは椀がきと同じ。
お湯が入っているので、椀がきより冷めにくいですが、
長くお湯につかっていると、そばがきの表面がヌルッとします。
そば茶入り そば粥
そば粉 ぬき実を使ったおいしい「そば茶入り そば粥」をご紹介します。
「あっ」という間にできる手軽な一品! ぜひご家庭でお試しください!
材料
- そば丸ぬき実 50g:
- 水 350cc
- そば茶 スプーン1杯ぐらい
- 塩 少々
お米のお粥でいうと7分粥の割合になります。そば茶と塩はお好みにより加減してください。
 丸ぬき実をさっと洗い、350ccの水に30分程度つけておきます。
丸ぬき実をさっと洗い、350ccの水に30分程度つけておきます。
炊く前にそば茶をいれます。
沸騰するまで、やや強火で炊きます。この際、ふきこぼれに注意してください。
この量で、約10分弱で沸騰しました。炊く時はふたをしてください。
 見た目はちょっと悪いですが…。
見た目はちょっと悪いですが…。
沸騰した後は弱火で15分〜20分ぐらい炊きます。
好みの柔らかさ・硬さがあるので、様子をみながら時間を調整してください。
 出来上がり。
出来上がり。
そば茶の香ばしい香りがおいしさを増す一品です。
ガレットとそば粉のクレープ
- そば粉で作れる!ガレット・クレープ生地
- フランス西端、大西洋に突き出した半島に位置するブルターニュ地方。ここの有名な食べ物にガレットとクレープがあります。そば粉で作るのがガレット、小麦粉で作るのがクレープです。
ガレットには、チーズや卵をソテーしてのせ、4辺を折ります。ガレットは食事、クレープはデザートといったところでしょうか。 - このガレットとクレープ、共にそば粉を使えば生地が作れます。フランス政府観光局オフィシャルサイトにも掲載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってください。
材料
- 牛乳か水 150cc
- 小麦粉(少し混ぜるとうまく仕上がります)
- そば粉 50g
- 卵 1個
- とかしバター 大さじ1
- 塩 ひとつまみ
- サラダ油 少々
調理方法
 そば粉をふるいにかけ、その中に牛乳・卵・とかしバター・塩を入れてしっかりと混ぜ合わせます。
そば粉をふるいにかけ、その中に牛乳・卵・とかしバター・塩を入れてしっかりと混ぜ合わせます。
とかしバターは、冷たい牛乳や卵と混ぜ合わせると固まることがあるので要注意です。
フライパンを熱し、生地を流し込み、円を描くように薄くのばして焼きます。
 火加減は弱すぎてもダメ。なかなか焼けません。中火くらいにしてください。
火加減は弱すぎてもダメ。なかなか焼けません。中火くらいにしてください。
均一に薄くのばすのが何よりの難関! 専用の鉄板と道具があれば、上手にできるのかもしれません…。
 出来上がったそば粉のクレープをアレンジ!
出来上がったそば粉のクレープをアレンジ!
市販のフルーツの缶詰とブルーべりージャムをのせました。
 メープルシロップだけでもおいしいですよ。
メープルシロップだけでもおいしいですよ。
温かい間にぜひ召し上がってください。
 ちょっとゆっくり出来る休日の朝食・昼食にいかがですか?
ちょっとゆっくり出来る休日の朝食・昼食にいかがですか?
写真は卵・香草いりウインナー・ベーコンを使っていますが、
ソテーやボイルをした魚介類、野菜を使うともっと豪華(?)になります。
 クレープ・ガレットの生地が残ったら、適当にちぎってオリーブオイルで揚げてみます。
クレープ・ガレットの生地が残ったら、適当にちぎってオリーブオイルで揚げてみます。
ピカタ風に、こんがりきつね色になるまで揚げます。
出来上がったら、油気を切って、ジャムやごまペーストをトッピング!
粉砂糖をふりかけても、一味違ったおやつになります。なぜかやめられないおいしさです。
そば粉を使ったあべかわ
 材料
材料
- そば粉(ちゅうそう粉) 50g
- 餅粉 50g
- 熱湯 75cc
- 作り方
 そば粉と餅粉を混ぜて、熱湯を注ぎ、「そばがき」の要領で練って、少し冷めてきたらこねます。
そば粉と餅粉を混ぜて、熱湯を注ぎ、「そばがき」の要領で練って、少し冷めてきたらこねます。
初めはお湯の量が少ないように感じますが、心配ありません。お湯が多すぎると、べたついて大変なことになってしまいます。 こねる時、手にひっつかないくらいのねばり加減にします。
こねる時、手にひっつかないくらいのねばり加減にします。
 団子をゆがくと膨れるため、平たく延ばします。
団子をゆがくと膨れるため、平たく延ばします。
厚みがあると口にした時に“モゴモゴ”とするので、
薄焼きせんべいぐらいの厚みがちょうどよいでしょう。 沸騰したお湯に団子を入れ、浮き上がった後、30秒から4分くらい煮ます。
沸騰したお湯に団子を入れ、浮き上がった後、30秒から4分くらい煮ます。
 あべかわ餅の要領で、きな粉をつけて出来上がりです。
あべかわ餅の要領で、きな粉をつけて出来上がりです。
お餅とは一味違った食感でとてもおいしいですよ!
ごまのペーストなどを塗ってもいいかも。いろいろと食べ比べてみてください。
そばぜんざい
 材料
材料
- そば粉(ちゅうそう粉) 50g
- 餅粉 50g
- 熱湯 75cc
餅粉を混ぜると、柔らかく弾力があります。
そば粉と餅粉の割合はお好みで・・・
- 作り方
 ひと口くらいの大きさにまるめて、沸騰したお湯の中に入れます。
ひと口くらいの大きさにまるめて、沸騰したお湯の中に入れます。
団子の場合も浮き上がってきてから、串がすっと通るくらいになるまでゆがきます。 後はおぜんざいに入れるだけ。
後はおぜんざいに入れるだけ。
そば団子の出来上がりです!
寒い冬にぴったりな、おいしいそばぜんざいができました。そば団子はあっさりとした味わいなため、ほかの汁物にも使えます。ぜひ一度お試しください。
二八そばの打ち方はこちらです。